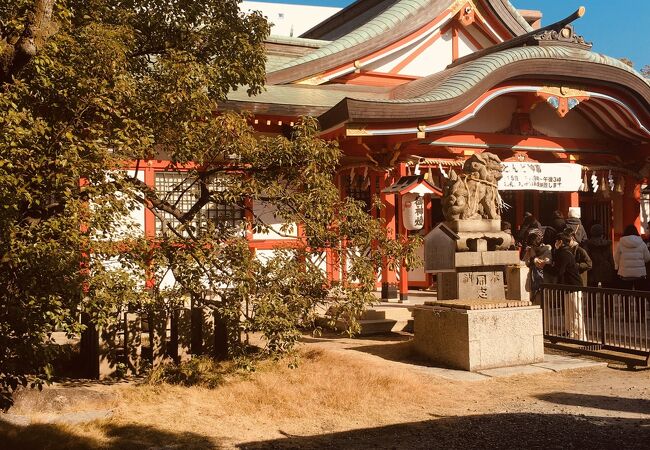大阪の寺・神社・教会 ランキング(2ページ)
ランキングを条件で絞り込む
- エリア
- カテゴリ
エリアを選ぶ
閉じる
- クチコミあり
- すべて
-
3.42
- アクセス
- 3.80
- 人混みの少なさ
- 3.92
- バリアフリー
- 3.38
- 見ごたえ
- 3.56
久太郎町4丁目渡辺に鎮座、「ざまさん」の名で親しまれ、昔から住居守護、旅行安全、安産の神として信仰されている。創建は、神功皇后が遠海から帰還した時、淀川河口の地に坐摩神を祀ったのが始まりとされる。一方、『延喜式』によると、天正11年(1583)、豊臣秀吉が大坂城を築くために、天満橋付近の渡辺橋の南詰にあった、摂津国西成郡(にしなりぐん)の氏神だった社を、地名とともに現在の地に移したと記されている。以降は、物売りや見世物などで賑わい、それをきっかけに周辺に古手屋、陶器問屋が集まるようになったそうだ。境内には、陶器神社があり、毎年7月21~23日には陶器祭が催される。 ...続きを見る
- アクセス
- 地下鉄御堂筋線「本町駅」から徒歩で2分
- 営業時間
- 7:30~17:00
- 休業日
- 無休
もっと見る
-
3.40
- アクセス
- 4.15
- 人混みの少なさ
- 4.18
- バリアフリー
- 4.02
- 見ごたえ
- 3.79
文禄5年(1596)本願寺第12代教如上人は、渡辺の地に大谷本願寺を建立し、慶長3年(1598)現在地に移った。同7年、京都に東本願寺が建立されるまで真宗大谷派の本山であった。昭和20年に戦火により焼失、同36年再建。境内に松尾芭蕉の最後の句を刻んだ碑がある。 ...続きを見る
- アクセス
- 地下鉄御堂筋線「本町駅」から徒歩で5分南へ
- 予算
- 無料
もっと見る
-
3.40
- アクセス
- 3.62
- 人混みの少なさ
- 3.83
- バリアフリー
- 2.53
- 見ごたえ
- 3.81
天王寺区の宰相山公園にあり、仁徳天皇・天照大神・月読命・素盞嗚命を祀る三光神社。社伝によれば、寛文元年(1661)に当社は南東方向にある鎌八幡の隣に移転されたが、その後宝永3年(1706)に再び現在地に戻ったという。古くは「日月山神社」とも、「姫山神社」とも呼ばれたらしい。明治11年(1908)に陸奥国青麻の三光宮の分霊を勧請・合祀したことから、「三光神社」と呼ばれ、今日に至っている。「三光さん」は中風封じの神として良く知られており、毎年6月1日から1週間の中風除け祈願の期間には、全国各地から参拝者がやってくる。また、境内は桜の名所としても知られるほか、大阪城と地下道でつながっていると伝えられる「真田の抜け穴」の跡がある。この抜け穴の脇には真田幸村の陣中での指揮姿の銅像が建っている。 ...続きを見る
- アクセス
-
1) 地下鉄長堀鶴見緑地線「玉造駅」から徒歩で2分
2) JR大阪環状線「玉造駅」から徒歩で5分
- 営業時間
- 9:30~16:00 利用時間は社務所の開いている時間
- 休業日
- 年中無休
- 予算
- 拝観無料
もっと見る
-
3.40
- アクセス
- 3.95
- 人混みの少なさ
- 3.86
- バリアフリー
- 2.35
- 見ごたえ
- 3.19
- アクセス
- 阪急電車・梅田駅の茶屋町口より徒歩約3分
-
3.40
- アクセス
- 3.34
- 人混みの少なさ
- 3.89
- バリアフリー
- 2.52
- 見ごたえ
- 3.21
地下鉄谷町線谷町九丁目駅下車徒歩5分。貞観8年(866)、清和天皇の勅令によって難波高津宮の遺跡が探され、あったと定められた地に仁徳天皇を祀る社が建立されたのが始まりとされている。700年後、正親町天皇の天正11年(1583)、豊臣秀吉が大坂城を築城した際にご神体を現在地に移したが、第2次世界大戦時の大阪大空襲で神社は悉く全焼。現在の社殿は、戦後に再建されたもの。同社は古典落語「高津の富」「高倉狐」「祟徳院」の舞台として知られ、古くから大坂町人の文化の中心地として賑わっていた。現在も境内にある「高津の富亭」で、五代目桂文枝一門による落語の寄席が定期的に行われている。また、境内に桂文枝の石碑も。春の高津宮桜祭は大勢の花見客で賑わい、夜桜はとくに評判だという。 ...続きを見る
- アクセス
- 地下鉄谷町線「谷町九丁目駅」から徒歩で5分
- 営業時間
- 9:00~16:30
もっと見る
-
-
3.39
- アクセス
- 3.78
- 人混みの少なさ
- 3.85
- バリアフリー
- 3.26
- 見ごたえ
- 3.72
ゴシック様式の尖塔窓・黄色や緑色の色ガラスで飾られた外観と、清楚で美しい空間の礼拝堂・聖堂を特徴にもつ、昭和初期のレトロ建築。
- アクセス
- 地下鉄・京阪「淀屋橋」駅から徒歩で5分
-
3.38
- アクセス
- 4.02
- 人混みの少なさ
- 4.04
- バリアフリー
- 3.28
- 見ごたえ
- 3.43
- アクセス
- JR東西線 新福島駅より約徒歩2分、JR大阪環状線 福島駅より約徒歩5分
-
3.38
- アクセス
- 3.57
- 人混みの少なさ
- 3.55
- バリアフリー
- 3.29
- 見ごたえ
- 3.47
地下鉄谷町線/堺筋線「南森町」下車北西へ約250m。蛭子(ひるこ)大神を祭神とし、「キタのえべっさん」として、ミナミの今宮戎神社とともに親しまれる堀川戎神社。6世紀中ごろの創建と伝えられる。止美連(とみのむらじ)吉雄が、蛭子神のお告げによって浪華堀江の芦辺で玉を拾い、これを神霊の代わりとして難波富島に祀ったのが始まりとされるが、文和(ぶんな)年間(1352~56)、当地に移築したそうだ。十日戎の日には参詣客が境内に入りきらないほどの混雑を見せ「商売繁盛で、ササ持って来い!」という景気のいい掛け声が、普段はひっそりとしている境内に響き渡る。そのほか、摂社の「榎木神社」は一般的に"地車稲荷"と称され、願いが叶うと地車囃子が聞こえてくるといわれており、参拝する人が多く見られる。 ...続きを見る
- アクセス
-
1) 地下鉄堺筋線・谷町線「南森町駅」から徒歩で3分
2) JR東西線「大阪天満宮駅」から徒歩で3分
- 営業時間
- 6:00~20:00
- 休業日
- 年中無休
もっと見る
-
3.38
- アクセス
- 3.56
- 人混みの少なさ
- 4.04
- バリアフリー
- 3.34
- 見ごたえ
- 3.40
地下鉄谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅から徒歩2分、四天王寺の四箇院のひとつである「施薬院」として推古天皇元年(593)に、聖徳太子によって建立された。施薬院とは、仏教の教えによって設けられたもので、薬草を栽培し、あまねく人々に病に応じてそれを与える福祉施設だった。後に聖徳太子が勝鬘経を人々に講ぜられ、経に登場するシュリーマーラー夫人(勝鬘夫人)の仏像を本堂に祀ったことから、当院は「勝鬘院(しょうまんいんあいぜんどう)」と呼ばれるようになった。また金堂には本尊として、良縁成就・夫婦和合で有名な愛染明王が奉安されていることから、「愛染堂」としても親しまれている。境内には、豊臣秀吉が再建した桃山時代の代表作である、多宝塔(国の重要文化財)のほか、飲むと愛が叶うといわれる「愛染めの霊水」があり、若い女性に人気だ。毎年6月30日、7月1・2日には、大阪の三大夏祭りのひとつとして有名な愛染祭が行われる。 ...続きを見る
- アクセス
- 地下鉄谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘駅」から徒歩で2分
- 休業日
- 年中無休
- 予算
- 参拝・拝観無料
もっと見る
-
3.37
- アクセス
- 3.78
- 人混みの少なさ
- 3.73
- バリアフリー
- 3.18
- 見ごたえ
- 3.58
- アクセス
- 大阪市営地下鉄谷町線 東梅田駅
- 営業時間
- 6:00~24:00(社務所 9:00~18:00)
もっと見る
-
-
3.37
- アクセス
- 3.70
- 人混みの少なさ
- 3.46
- バリアフリー
- 3.34
- 見ごたえ
- 3.40
- アクセス
- 地下鉄御堂筋線梅田駅から徒歩10分
-
3.37
- アクセス
- 3.58
- 人混みの少なさ
- 3.62
- バリアフリー
- 2.95
- 見ごたえ
- 3.93
- 住所
- 大阪府大阪市天王寺区四天王寺町1-1-18
-
3.37
- アクセス
- 2.20
- 人混みの少なさ
- 3.59
- バリアフリー
- 1.42
- 見ごたえ
- 4.00
- アクセス
-
泉北高速 和泉中央駅からバス そこから山道を30分以上
粉河寺から徒歩7時間弱
河内長野駅から徒歩2時間半
-
3.36
- アクセス
- 3.48
- 人混みの少なさ
- 3.88
- バリアフリー
- 2.94
- 見ごたえ
- 3.86
大阪市中央区玉造に鎮座する神社。創建は垂仁天皇18年(西暦紀元前12)と伝えられ、古代、付近一帯は「玉作岡」と呼ばれ、勾玉(まがたま)などをつくる玉作部が居住しており、それが現在の玉造の名の起こりとなったそうだ。豊臣時代には大阪城の守護神として知られ、またここで豊臣秀吉・秀頼・淀殿などが千利休のお点前で茶会を催していたと伝えられている。同社は天正4年(1576)の兵乱やその後の大坂城落城、また第二次世界大戦時の大空襲などによりことごとく焼失し、現在の社殿は戦後に再建されたもの。境内には秀頼奉納の鳥居や千利休の顕彰碑などのほか、難波玉造資料館もあり、古代玉遺物、玉の歴史や玉作り工程、古代土器など貴重な資料が展示されている。 ...続きを見る
- アクセス
-
1) JR大阪環状線・地下鉄鶴見緑地線「森ノ宮駅」から徒歩で5分
2) JR大阪環状線・地下鉄鶴見緑地線「玉造駅」から徒歩で5分
- 営業時間
- お参り時間は日の出から日没まで
- 休業日
- 無休
- 予算
- 拝観無料
もっと見る
-
3.36
- アクセス
- 3.65
- 人混みの少なさ
- 3.80
- バリアフリー
- 3.50
- 見ごたえ
- 3.93
厄除観音として広く知られる古刹です。行基が開き、新西国霊場第四番札所としても名高いです。神仏霊場大阪十二番、和泉西国第二十六番礼所。天平16年(744年)聖武天皇の勅願により行基が開基したと伝えられています。最盛期には七堂と僧坊百三十余を有する大伽藍を誇りました。天正13年(1585年)豊臣秀吉の兵火で焼失し、現在の本堂は文化8年(1811年)に再建されたものです。本尊は「厄除の観音様」として信仰が厚いです。伝統行事の「千本餅つき」は、ご本尊の観音出現を祝い、行基が先導された十六童子と共に木の棒で歌に合わせて餅をつき、ご本尊にお供えしたのが始まりで、以来現在まで伝えられています。※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催が変更になる場合があります。詳しくは各寺社等の公式ホームページでご確認ください。 ...続きを見る
- アクセス
- その他 南海電鉄本線「貝塚駅」より水間鉄道に乗り換え、終点「水間観音駅」下車 徒歩10分
- 予算
- 【料金】 拝観無料
もっと見る
-
宿公式サイトから予約できる大阪のホテルスポンサー提供
-
大阪への旅行情報
-
3.36
- アクセス
- 3.82
- 人混みの少なさ
- 3.98
- バリアフリー
- 2.93
- 見ごたえ
- 3.90
菅原道真公ゆかりの地ということで、道明寺は学問の神としての信仰を集めました。この地は、菅原氏・土師氏の祖先に当たる野見宿禰の所領地と伝え、野見宿禰の遠祖である天穂日命を祀る土師神社がありました。仏教伝来後、土師氏の氏寺である土師寺が建立されました。平安時代、土師寺には菅原道真公のおばに当たる覚寿尼公が住んでおり、道真公も時々この寺を訪れていました。延喜元年(901年)、大宰府に左遷される途中にも立ち寄って、覚寿尼公との別れを惜しみました。道真公遺愛の品と伝える硯、鏡等が神宝として伝わり、6点が国宝の指定を受けています。道真自刻を祀り、土師寺を道明寺に改称しました。道真公ゆかりの地ということで、道明寺は学問の神としての信仰を集めました。本殿背後の梅園には見ごろの2月になると約80種、800本の梅が美しく咲き、「大阪みどりの百選」にも選ばれています。また、拝殿そばの「常成梅(じょうなりうめ)」は一年中実をつけたままの珍しい梅です。毎年1月25日に行われる「初天神うそかえ祭」は災難除けの神事で、前年についたウソを流そうと多くの参拝者が訪れます。※イベント開催は変更になる可能性があります。詳しくは各イベントの公式ホームページでご確認ください。 ...続きを見る
- アクセス
- その他 近鉄南大阪線「道明寺駅」より徒歩3分
-
37
3.36- アクセス
- 3.85
- 人混みの少なさ
- 3.88
- バリアフリー
- 3.12
- 見ごたえ
- 3.79
西国三十三所第二十二番礼所の名刹です。「庖丁道の祖」で知られる藤原山蔭により創建されました。毎年4月18日の「山蔭流庖丁式」が有名です。総持寺は西国第二十二番の名刹として知られる高野山真言宗の寺院です。開山の中納言藤原山蔭は、平安時代の貴族で「庖丁道の祖」「料理の神」として知られています。山蔭が幼き頃、淀川で父君が助けた大亀に、山蔭が命を助けられたという「亀の恩返し」の奇瑞により仁和2年(886)に創建されました。本尊は「亀の背に立つ」千手観音です。毎年4月18日に行われる「山蔭流庖丁式」は、庖丁士が、手で魚を触れることなく庖丁と真名箸で調理します。華麗な庖丁さばきが見どころです。境内には料理上達を願い、使わなくなった庖丁を奉納する庖丁塚があります。お祭り ...続きを見る
- アクセス
- その他 阪急京都線「総持寺駅」より徒歩5分、JR東海道線「JR総持寺駅」より徒歩5分、名神高速道路茨木ICより10分
- 予算
- 【料金】 入山料:無料駐車料:参拝者駐車場 最初の40分300円、以降20分毎に100円
もっと見る
-
3.36
- アクセス
- 3.33
- 人混みの少なさ
- 3.67
- バリアフリー
- 3.31
- 見ごたえ
- 3.82
役行者が開基し、日本四弁財天のひとつとされる本尊をもつ名刹です。日本の宝くじ発祥の地としても有名です。白雉元年(650年)、役行者が箕面の滝で修行中、龍樹菩薩より法を授かり滝の下に弁財天を刻んで堂宇に安置したと伝えられ、古くは箕面寺と呼ばれました。江戸期には「箕面の福富」を発行したことから、宝くじ発祥の寺とも知られており、その様子は「摂津名所図会」にも描かれています。財運、芸能上達の功徳を持つ弁財天には、年中参拝者が訪れます。また山岳修験道の根本道場でもあり、年中行事である大護摩供には近畿一円より山伏が集結します。 ...続きを見る
- アクセス
- その他 阪急箕面線「箕面駅」徒歩15分
- 営業時間
- 9:00~16:00、休日:拝観自由
もっと見る
-
3.36
- アクセス
- 3.44
- 人混みの少なさ
- 3.82
- バリアフリー
- 3.08
- 見ごたえ
- 4.22
南河内の英雄・楠木正成ゆかりの寺です。国宝の如意輪観世音菩薩や金堂の他に文化財が多数ある高野山真言宗の古刹です。大阪・奈良・和歌山の三県の境に位置する観心寺は、701年、役行者によって開創されたとされる古刹です。弘仁6年(815)、弘法大師空海が真言宗の道場として再建しました。開創当初は「雲心寺」と呼ばれましたが、再建の際、空海が如意輪観世音菩薩(七星如意輪観世音菩薩)を刻んで本尊とし、寺号を「観心寺」と改めました。国宝である本尊は、毎年4月17・18日の2日間だけ開扉されています。木立が繁る境内には、弘法大師の弟子である実恵の墓や、第97代後村上天皇御陵、楠木正成の墓などがあります。梅、桜、紅葉の名所でもあり、関西花の寺25番霊場に数えられる他、新西国客番霊場、仏塔古寺13番霊場でもあります。※イベント開催は変更になる可能性があります。詳しくは各イベントの公式ホームページでご確認ください。 ...続きを見る
- アクセス
- その他 南海高野線「河内長野駅」・近鉄「河内長野駅」より、南海バス「小吹台行」「金剛ロープウェイ行」に乗り換え「観心寺」下車すぐ
- 予算
- 【料金】 大人 300円、小中学生 100円毎年4月17日、18日は本尊御開帳日特別拝観料 700円
もっと見る
-
3.36
- アクセス
- 3.27
- 人混みの少なさ
- 3.57
- バリアフリー
- 3.33
- 見ごたえ
- 3.19
古くから境内の土や砂が悪い方位を祓う=方災除けの神として信仰を集め、いまも家の新築や転居の際の厄除け祈願に大勢の参拝者が訪れます。崇神天皇8年(西暦前90)12月29日、勅願により創建されたと伝えられます。摂津・河内・和泉の三国の境の「三国山」と呼ばれる地(現:三国ヶ丘)にあり、奈良時代には人馬往来の要衝でした。また平安時代には熊野への参詣者が必ず立ち寄り、旅の安全を祈ったといわれています。どの国にも属さない、方位のない清地として、古くから境内の土や砂が悪い方位を祓う=方災除けの神として信仰を集め、いまも家の新築や転居の際の厄除け祈願に大勢の参拝者が訪れます。出かけなければならない方向が良くない時に、一度別方向に向かってから出かける方違い(かたたがい)の風習によって、お参りする人も多いです。毎年5月31日のちまき祭は故事にならい、菰(こも)の葉で包んだちまきが氏子らに配られます。※イベント開催は変更になる可能性があります。詳しくは各イベントの公式ホームページでご確認ください。 ...続きを見る
- アクセス
- その他 南海高野線「堺東駅」から徒歩7分、JR阪和線「堺市駅」から徒歩15分
- 予算
- 【料金】 拝観自由
もっと見る
- 1
- 2
※施設情報については、時間の経過による変化などにより、必ずしも正確でない情報が当サイトに掲載されている可能性もあります。